
連続小説

作 米島健二
オープニングテーマ『冬の星座』 by Kenji Yoneshima
18歳の頃、放浪の直前に作った歌を思い出しながら打ち込んでみた。GM音源用。
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安定した暇な時に読んでほしい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 著者略歴 Kenji Yoneshima 昭和35年9月20日生。精神分裂病2級。ホームヘルパー2級。北九州市門司区にて同じく分裂病の妻と二人暮らし。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−1.悪夢− 普通に会話して、普通に笑う。でも心の中は違う別の意味を探る。 例えばそっちが「赤」と言うと、こっちは百個くらい連想して百1個目の「とうもろこし」と答える。 会話できないと怒る。まるで違う所で笑う。でもそっちの気持はわかる。 日が当たる所は神とつながり、影を走る時には悪魔と通じる。 太陽を拝む。光は知性をもっている。知性はこっちに関わりたがってる。暗闇には魑魅魍魎がはびこり、甘い言葉でこっちを取り込もうとしてる。 低いうなりは暴力で、高いキーンという音は気高いものを示す。そっちの前でこっちは皇族として背筋を伸ばす。ほんとつかれるね。背伸びまでしてる。 耳を塞ぐと体内の回路の音が聞こえる。いつの間にか改造手術を受けている。 脳内合唱団は、都営地下鉄の中で特によく聞こえる。坂本九もいる。 一つ一つの出来事に深い意味があるように思う。関連しないはずの事が無理やり結び合う。生きる事の謎がいとも簡単に解ける。3秒で花が咲き、コンマ1秒で枯れる。半年たっても枯れたまま。 こっちが影を押さえている間、そっちの時間は止まり、動かない。 袖すりあうのも多少の縁。500年ぶりに再会できた。なのに、すれ違うだけ。 何千人がかりで、念じて、こっちの心臓を止めようとしてる。こっちは一人きりなのに。 気を抜いた瞬間にやられる。おちおち寝ていられない。 「ケンちゃん、鍵あけて」「鍵あけてよ」そちらから助けを求める声。どこに閉じ込められてるの。どうやって助けてあげたらいいの。もう死んでるの。想像が膨らむと恐怖も増幅する。多勢いるふりして、そっちも本当は一人なんじゃないの? 胸をかきむしって毛布を蹴っ飛ばして飛び起きた。 心臓はばくばくなっている。バクは夢を食うはずじゃないのか。むやみに腹が立つ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−2.お茶の時間− ずうっとただ見てるだけで、恋してしまった。あの時、やっと初めて会話した間、何分くらい? 息が出来なかった。脳内を花火がキュルキュル回転した。意味の無い言葉を交わして。失神するほど楽しい気分。湯飲みに茶の葉を入れて、二人で笑った。 あの後そっちは泣きだして、何故なんだろう。あれっきりもう会えなくなる事を、多分感じていたのかな。静かに泣いたね。その後僕は吼えるように慟哭したのだよ。引き裂かれたんだろ僕たち。 去年から二人暮し。同じ障害者。幸せかって? そっちのようにテレパシーは使えない。心配ないよ。その方が長くつきあえると思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−3.舞台− 感謝の気持。お詫びかも知れない。多分もう会えないし、会わないからね。 デートの日は何故ドシャ降りだったのかとか、日常が全部演技なのだとか儀式なのだとか、そういう事ではない。お互いもう特別の人ではないから。神が降りてきたってもうどうってことない。悪魔がささやいたって屁でもない。 耳を劈く雷鳴のあと黒雲が押し寄せて、あわてて入ったコンビニの中で高笑いして。店の女の子と配達の男の子が喧嘩してた。下手な演技で。どっちも見たことあるぞ。名前は思い出せないけど。笑うしかないだろ。ありがとう僕のために。 買い物するのも、食事をするのも、楽しくて怖いものなし。TDLのアトラクションの100倍楽しい。気が狂いそう。おまけに洗霊まで受けて。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−5.悟りの時− よく晴れた春の日。鶯が鳴く。狭いベランダから高速道路を見下ろした。強い風と車の音が区別できなかった。 亡父のマッサージチェアに正座して太陽を見つめた。 意識をその恒星の中心まで高める。すると、自分の存在まで光とともに宇宙に拡散していった。何者かに届いているという実感があった。それが神なのか生き物なのか、その何者かは伝えた。「おまえを待っている」と。その一瞬で、ある時宇宙が澄み渡るように、僕の脳も頭蓋骨をつきやぶって晴れていった。 飛べると信じた。近づけると感じた。 吹き上げる風はまだ少し冷たく、僕の肩をがっちりつかむ日光は柔らかだった。 眼下で電線が悲鳴をあげていた。 椅子の上に立った。小刻みに大きく震える肉体を静める事すら忘れていた。右足をベランダの手すりに乗せ、ホイッスルが鳴るのを待った。 頭の中を無限音階が流れはじめ、どんどんオクターブを上げていき、人の可聴域を超えて、音はやがて電波になり光になり、光はやがて、意識の矢になって、それでも上昇は続いた。 痺れた足は、5センチほどふわふわ宙に浮かんだ。 風にあおられたカラスアゲハが数匹、頭上を回る。 遠くからラーメン屋のチャルメラのような音をたててパトカーが集まってくる。 遠くの高層ビルから望遠レンズが狙っていた。 「飛べ、飛べ」民衆の声。 「死ね、死ね」と地獄の声。 すーっと空に吸い込まれていった。 上昇する意識とは逆に、肉体は自由落下していった。 肉体に魂が戻るまでの数時間、右半身が不随になった。 「勢いよく飛んで良かったな」飛距離に驚いた警察が言ったそうだ。 真下に落ちてたらコンクリでペチャンコに死んでた。 四月の草花に覆われた坂というか崖を転がりながら着地したため、全身無数の擦り傷と精神以外に異常は無かった。 「別に死のうとしたんじゃない」けれどうまく説明出来なかった。警察も深く事情は聞かずに、精神科へ入院を勧めた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
−6.天上の楽音− 僕はあの時死んだ。でももし死なずにいたら――可能性の宇宙が一瞬ぱくっと口を開けて、君が待つこの宇宙にワープしてきた。そんな感じ。 死んじまったら負けで、おまけに弱虫だとか思わない。勇気あるぞ偉いぞとも思わない。どうせいつか死ぬのである。事故であろうと故意であろうと、神に近づく一つの道に違いない。生きていたらもっと近づけてたかも知れない。だが善悪をとやかく語りたくはない。真理は人の生き死にとは別にある。運命は人の手に負えない。ともかく僕は自分の意思とは関わりなく、より神に近いこの世に再生したと感じている。以前の僕は確かに死んだんだ。 話は少しさかのぼる。 東京都花小金井。平成5年。秋から冬にかけて。最初に入院する直前の数ヶ月は忘れない。人が見ると不可解で、妄想に支配された僕の行動は、巡礼のような日々だった。 拡張指導員でもあった僕は焦燥に追われて新聞屋に逃げ込むのがパターンの一つで、そんな隠れ家の一つが花小金井にあった。 開発資金切れのソフト会社をそそくさとたたんで、毎朝3時と、夕方2時の2回、駅前の一方通行を逆走し交番の前だけバイクを押し歩き、ASAへ通った。200軒くらいの配達先を最後まで配り通せたことは一度も無い。20軒ほど迷いながら配って、残りは逆巻に交代してもらうのが常だった。ただでさえ入り組んだ花小金井の町、道を覚える能力の無い僕にとって、逆巻はガイドで、実の所、僕個人の使用人のようだった。金は僕じゃなく朝日が払っていたのだけど。 配達と睡眠の間の昼と夕方の時間は、本来は拡張の仕事をしなければならないのだが、自室で野心たっぷりのソフト開発をしていた。発病した後、僕のハードディスクの膨大なソース群に、「まるでわからん」と同僚も苦笑した。 何を作ろうとしていたかと言うと、当時、僕も何が生まれるのか実は分かっていなかった。神のみぞ知る。 ひらめく度に奇妙な部品が増殖していった。組み合わせるとさらに奇妙な構造となり、最終的に実行してみるまで、どんな動きをするのか、解析不能だった。 ともかく僕は外面では花小金井全町民の応援を受けてひた走る新聞少年のふりをしていた。同情をかって契約を取るのが得意であった。僕が拡張員の背後に立って、ちょこんと頭を下げるだけで、不良の兄ちゃんであろうとヤクザのおいちゃんであろうと、簡単に長期契約を取ることが出来た。 我ながら涙ぐましい努力で、とにかく走るのは走った。カブに乗って走りながらも知性のアルゴリズムを考え続けた。荷台に高く積み上げた新聞をほったらかして、 配達の最短経路を算出するロジックを考え続けたりしていた。四畳半の隠れ家は、機材と書籍で寝る場も無かった。 忘れられない。一日に2回だけ外に出る。ASAのジャンパーで街にくるまると、木琴のような音がこんこんと雪のように降ってくる。応援歌のように丸めた背中に降ってきて熱く恥ずかしい思いがする。降り注ぐ音は光を放ってジャンパーに当たって砕けて、僕の人生にいちいちBGMを流す。良く知った曲であるようで、初めて聴くようでもある。一番記憶に近いメロディーは「上を向いて歩こう」であった気がする。雨や風の音、それから街の雑踏と重なって、ささやかに美しく鳴り響いていた。せつない。 この世界は音楽で溢れており、脳はスイッチを入れてチューニングすれば、どのチャンネルの曲も流すことが出来る。そう思って聴くとどんな曲にも聞こえる。 悟りを得た高僧が祈る時、脳はシータ波を発するそうであるが、それと同じ7ヘルツ前後で、地球に意識を飛ばすと、丁度光の速度が1秒間に7周半だから、シンクロして増幅したシータ波はガイアの意識に触れるのだなどと勝手に理由をつけて、バンアレン帯あたりに念を飛ばした。そこには多くのイルカや地球人の深層意識が渦巻いており、そこから僕の肝心のアイデアを盗まれないように炎の壁を築いた。風呂に水を入れながらヤッホーと叫ぶとフィンランドの湖にまで声が届く気がするだろう。だって水が繋がってるじゃないか。僕の心は誰かに読まれている。僕の見るものは誰かに見られている。僕の感じることは誰かに盗まれている。どこか遠くの何だろうか。隣に潜む人だろうか。いつの時代の人だろうか。正体は決してあらわさない。 いつかしらそれこそハイヤーパワーなのだと気づくことになった。 神のせいにすれば気が楽だ。何でもお見通しと言うではないか。知ったような顔で僕に微笑みかける者には、軽蔑の笑みを返した。「お前なんかに読まれるもんか」僕は気高いものと繋がっている。同時に悪魔とも。 僕たちは普段、五感の刺激に縛られていて気づかないけれど、多くの意識とつながっている。一度脳と体の繋がりを断ち切ると、身体からの神経刺激を失った脳は、宇宙からの信号に向けて回路を編成しなおす。そうするとそれまで個であった意識が多くの意識との交信を開始するのだ。突如見知らぬ街の絵を描き出したり、交響曲を書いたり、意味不明の写経を始めたり、そんな経験を持つ僕らの仲間は多勢いる。 人間がこの宇宙を全て理解できるとは到底思っていない。だから理解している範囲が宇宙だと思い込んでいる。だから突然ささやきだした別の意識に僕らはパニクってしまったわけだ。 目立たないように。目立たないように。そう思ってうつむいて、誰とも目を合わさないように、祈るように、僕は一人でパソコンに向かった。ひたすら自分の脳から膿を吐き出すように、新しいコードを書き続けた。それが僕の写経であった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
−7.紀元杉− そもそも記憶というのは鮮明な部分と曖昧模糊な部分があるものだが、僕の場合は極端だ。肌の感触までリアルに覚えてる部分と、全く欠けてる部分が交錯している。 推測するに28、9歳の頃だったと思う。確か最初に入院する三、四年前。既に症状に耐えられなくなっていた。夏が終わる頃。 どうやって鹿児島空港まで行ったのか覚えてない。気がついたら屋久島行きのセスナで切り立った盆地を旋回上昇していた。迫る山肌と気流のせいで、墜落するんじゃないかと感じた。それもいいかとぼんやり思った。 空港からあてもなく乗ったタクシーが、「観光?」「まあみてよ」と島で一番展望がいい小山に運んでくれた。 パノラマで青い海と緑の山と一枚岩を叩き落ちる銀色の滝が見渡せた。滝は強烈なマイナスイオンを発生させながら蠢いており、九州一の名山は雲を巻いていた。羽衣をまとった天女が3人手招きをしているように見えた。スローモーション。自然の響き。人工物は一切姿をくらましている、神による景観に圧倒され、いきなり金属バットで後頭部を殴られたようなショックがあった。 車に戻ると運転手は、にやっと笑って「で、どちらへ?」。とりあえず何処か静かな宿と言った。運転手は「それなら」と自分の実家へと山道をさらに登った。 遊んでいても十分暮らせるほど、ソフトの著作権収入が入っていた。だけど遊ぶ気力が無い。とにかくじっと休んでいたかった。とにかく癒されたかった。けれどじっとしてられず、しかし何処へ行っても落ち着かず、実際何をやっても楽しめない。だからこの島に特に何か期待して来た訳ではなかった。流れ着いたという感じ。 運転手の家は、いわゆる民宿で、他に客はいなかった。案内された部屋は縁側に面した6畳和室だった。トイレとか風呂とか食事とかどうなってたのかは記憶にない。縁側から顔を出して、夜空を見ながら寝たら雨で顔が濡れた。 着いた日は好天だったが、それから雨はしばらく続いた。三、四日寝て過ごしてたら、あがったので、薪割りをしていた運転手が「屋久杉見る?」山道を数時間かけて連れていってくれた。 『紀元杉』は山道から森の中に入って少し下った所にいた。そこだけ少し開けた部屋になっていた。田舎育ちの僕には、特に異空間ということもなく、ごく普通の森の中といった印象だった。子供の頃遊んだ篠崎山の神社の大木の感触を思い出した。 大勢の猿や鹿や人の手でつるつるになった幹に、幼子が母にすがるように抱きついた。回した両手は、はるかに届かない。 「会いにきてくれてありがとう」と知らない女性の声がした。 上空は森林の枝や葉に隠れているのだが、苔や濡れた草が放つ光や神木のエネルギーのせいか、暗くは感じなかった。それどころか幻惑された視覚はまばゆい羽の妖精や森に漂うフィトンチッドのせいで眩むほどだった。東京で悩まされた魑魅魍魎がはびこる闇とは異なり、穏やかで純粋なものの光が飛び交っていた。 紀元杉の太い根が編み上げたゆりかごに丸くなって、うとうとした。 心地よい声がえんえんと昔話のようなものを語っていた。 旅の間中聴いていた宮下富実夫の音楽が、耳に焼き付いていて背景に流れた。 頭の頂点にキリで穴をあけて、甘く香る樹液をたらたらと注ぎ込まれているような、パニックと陶酔の交じり合う感触がした。 ふいにもよおして、誰もいないのをいい事に立小便をした。近年屋久島の環境破壊の一因として咎められる行為らしい。鳥の声、せせらぎの音。ひんやりした森の中。ここでは、もよおさない人の方が少ないらしい。 ろくに人と話ができなくなっていた僕が、何時間、森と会話したのか? 運転手が降りてきて「帰ろう」と紀元杉に向かって言った。 生きる意味を探すとか大げさな旅ではなかったと思う。仕事とか恋愛とか十代からの成り上がり志向人生に少し疲れていたのだろう。青年期の終わりに対する焦燥感だったのかも。病気だから悩んだのか? 悩んだから病気になったのか? 判らん。とにかく我が心に起きた異常に関して何か答を求めていた。 答は何も見つからなかったが、少し元気が出たらしい。再び僕の主戦場である東京へ戻る事にした。 帰りは船だったと思う。が、ほとんど覚えてない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
−8.声− 幻聴と言うと怖いイメージがある。実際、悪魔の声だったり念仏だったりする事が多い。自分の中の恐怖がイメージを育てるためだと思う。 おかしなこともある。脳内ラジオ局から、たけしとさんまの漫才が聞こえてきて、何話してるのかよく判らないくせに自分の事を話題にしていると思い込んで、笑い転げたりして、周囲を嘆かす。 さらに、とてもせつない幻聴もある。もう決して会う事のない人の声である。 その朝、心地よいチューブラベルの音で目が覚めた。ら、風鈴の音だった。だから、夏だと思う。そして、とても小さな声で、「おはよう」。U子の声だった。 U子は僕が東京へ出たあと死んでしまったはずなので、一瞬にして胸が真空になった。 それから時々、目覚める時に聞こえるようになった。しかし結局「おはよう」としか言わないので、すぐに慣れたのだが、最初は戸惑った。朝から物悲しい気分に陥ってしまうのだ。彼女が死んだのは十九か二十歳の頃だと思う。死んでから二年くらいたっている。事故だと聞いていた。でもなんだかそうでない気がしてきた。ずっと気になってたのだろう。そればかりか事故は僕のせいなのだと確信するまでに妄想が膨らんでいった。 U子は高校の部活の仲間でピッコロを吹いていた。僕とは特に恋人というわけではなく、たいがい一緒にいる、近しい友という感じ。17歳の時、僕がひどい失恋をして、鬱状態になった時に、えらい親身になってくれた。でも高校を出て、僕は東京でしがないフリーター。彼女は地元の大学に通うお嬢様。もうその時住む世界がはっきり分かれてしまった筈で。そのくらいの関係。亡くなったのを聞いたのが事故から数ヶ月も過ぎてからだったし、帰省の金も暇も持たなかったので、葬式はおろか、線香の一本も未だにあげてない。 でも在学中、一度だけ手紙で、彼女から告白された。「身も心も」そう書いてあった。身も心もって?、よく分からなかった。その時、どう処理したのかも覚えていない。僕は下級生とつきあっていたし、彼女もそれを知っていた。事実としてその前も後も、彼女との関係は変わらなかったが、心の底ではどうだったろう。 肉体を離れた魂とか心霊とか、はなから信じていなかった。今でこそハイアーパワー(HP)の存在を認めているが、当時はそれすら無くて、刹那的にどういう事なのか不安な思いをした。当然、精神の病気という事も考えた。だが、日常困るような段階では無かったし、自分の心が弱いせいだと、心身を鍛える事にせいを出して紛らしていた。しかし時々ちくちく痛くなる虫歯のようなもので、だんだんと深く浸食されてゆく病気は、鍛えて治るものではないようだ。それでも医学書よりはニューサイエンスや精神世界系の本を読んだりしていた。進んでいく痴呆と詰め込んでいく新しい知識が妙なバランスで人格に影響を与えていった。 「おはよう」しか言わないU子が、実はいつも僕の傍にいるのだという事を感じる時があった。二度の交通事故。転落。亡くなった人の魂がHPになるなんて、証明できないから、考えるのも馬鹿らしいが、僕が覚えている間は、U子は僕の記憶や体験の中に生き続けていると考えることは出来る。そればかりか成長している気がする。U子が何より美しかったし、信じられないくらい綺麗な字を書く女だったし、何よりはかなかったから、HPがそのイメージを借りて、僕に何か伝えようとしている事はうなづけた。蛇や蛙の姿よりはなんぼもマシだから。僕に声をかけるU子が、実際にあのU子では無いという事は当然理解出来ていた。でも頭で理解できても、心はしくしく痛んだ。神様もなんでそんな意地悪なことをするんだ。 それから、僕は生きていくのに、常に自分でない目、U子や神の目を、意識して、演ずるようになっていったと思う。いつも見られている、聞かれている、そういう意識が頭の隅にあった。僕の身体が僕の意識の支配から離れていった時も、その目は僕を見張り、縛っていた。守ってくれていたとも思える。 地下鉄の中で聞こえる天使の合唱団と同じくらい、U子の声を僕は気にいっていたのだが、40過ぎて結婚してからは、しだいに聞こえなくなった。今は自分の中というより、むしろ妻の中にU子の存在を感じることが多い。もちろん妻とU子の間に面識は無い。 |
挿入曲 『voice』 by Kenji Yoneshima 4度目の入院中に作った。 I feel your voice this morning, so prity, so far away... 僕の心に力が溢れる 遠くはなれ見えなくても 天の鏡、君を映し出す・・・ その時、脳の中ではドーパミンとかΒエンドルフィンとかのせいで超過敏の部分と超鈍感な部分に分裂している。僕は麻薬などやったことないけど、似たような状況だと推測できる。実際、音や光の僅かな刺激が万華鏡のように無限に反射しあって、どうにもならなくなる。同時に焦点の合ってない物は存在すら消滅してしまう。 その頃僕はまだ若く、夢を抱いていた。22歳くらいだったと思う。N88Basic(86)で夢幻投影というフロッピイディスクの同人誌を作っていた頃のこと。といっても仲間内に見せるだけで、どの世間にも発表はしていなかった。創刊号は音だけをテープに移してフォーライフに送ったりもしたが、完成度は低かった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
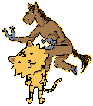 |
|
イラストはMS-Officeのクリップアートから持ってきた。こんな使い方していいのかな? 一日中タマネギに触っていると、手が洗っても洗ってもタマネギ臭い。涙はそのせいだったのかも・・・。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
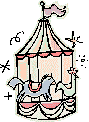 From ms-Office Clip Art  Wendy-MRS-IF1 |
|
今回、横文字とかが色々出てきますが、分からない言葉は読み飛ばして下さい。僕も実はよおっとわかってなくて使ってるんです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ミヤ王 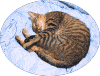 トラ王 |
|
普通の日本人ならビザ無しで入国できるのに、精神障害者がアメリカに入国するためには、ビザを取らねばならない。介護者無し、妻も僕も障害者なので。その為に必要な書類として何万円も出して横浜の米国大使館ご指定病院の医師から診断書を取得しなければならない。そしてそういう手続きを経た上でも、空港で入国を拒否される場合もあると、旅行会社から説明を受けた(暗にお断り)。犯罪者扱いですか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
僕の開発したMRSシステムの凄いところは、ライブハウスの照明装置を音楽と同期して制御できる点だと思う。照明の光量、色、位置の組み合わせを音楽と一緒にプログラミングできる。そしてそれをパソコン画面でシミュレート出来る。 横浜に倉庫を借りて、装置を組み上げて試験とデモンストレーションをやったり、メジャーなバンド数組の事務所へ営業に回ったりもしたが、契約できなかった。マイナーなバンドは照明なんかライブハウス任せというのが殆どだから、最初から相手にしていなっかった。例のゴーグルなどのシステムを渋谷のリラクゼーションハウスに10セット納品して得た僅かな利益も、倉庫に吸い込まれた。 著名な照明アーティストというのも知らなかったし、まだ時代が若すぎたのだと思う。 マイケルジャクソンなどにも真剣コンタクトを取ろうとしたが無理に決まってた。 一人横浜の倉庫で。一人で動かせるんだ。ラジオから拾ったランダムなノイズでシステムを動かしていると。ひとりでに開いた倉庫のドアから、横浜博覧祭の大輪の観覧車が寂しく回転していた。それは歌手のいない空間をサーチする倉庫内の照明と同期して光り、色を変えて回っていた。この地球も僕が動かしているのではないか。ふとそんな気さえしてきて、港の灯りや高層ビルの衝突避けのチカチカランプを眺めていたら泣けてきた。何やってるんだろう。 これは、もう自分でバンドを作るしかないや。そう思って昔の仲間に電話すると、彼らも30代、それぞれ銀行員やメーカーの技師や専業主婦などになっていて、相手にしてくれなかった。 いいや一人で。僕にはコンピューターが憑依していた。実験やデモ用に作った10曲ぐらいを、商業用に書きかえることにした。ここまでの苦労を考えたら、そんな事、簡単に出来ると思っていた。ところが作詞がどうにも出来なくて、頭を冷やす旅にも出たが。前述の通り、無駄に終わった。 ノイローゼから統合失調に移るように、時代はDOSからWindowsに変わろうとしていた。僕のシステムはNECのPC98というパソコンのハードに極限まで依存しており、Windowsへの移植は基本設計から変更しなければならない。一人でやるには、ちょっと気の遠くなるような作業だった。中途で投げ出してしまった。僕が建築設計士だとして、自分で設計した家をなんとか自分で建てられたとしても、超高層ビルを設計できても一人で建てることなど出来ない。そういう事だ。 その頃、常に聞こえていたのは、宇宙からの背景輻射だと思っていた。耳鳴りというと簡単だけど、その信号の意味をつい考え込んでしまうのが常だった。幻聴とまではいかない、かといえ頭の中の音楽というほど、当たり前でない音。そして回転するイメージ。浮き沈みはあったけど、大方順風満帆だった20代が終わり、何か大変な事が起こるような、漠然とした名状しがたい不安が襲い掛かる。馬鹿げた開発にのめり込んでいるという実感はあったが、同時に使命みたいなものを感じていた。人に感動を与える事が目的としてあった筈で、ビジネスというか金儲けがその夢を陳腐な物に落としめていった。 3人だけ残っていた社員も一時に解雇し、たった一人の会社になった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
どぶネズミを生で食ってでも、生き延びてやる。それが自力で生きるという事か。 10月から、12月にかけて。 平成五年の冬の旅は、山手線の各駅を順繰りに寝床にしながら、東京を歩いた。 ソフト開発が暗礁に乗り上げた。写経も続かない。経済的にも緊迫してくる。おまけにつきあってた女に見つかり、無責任と罵倒される。ノイローゼが高じて、妄想にはまった。そういう事か。 持ち物は、手提げのビジネスバッグ一つ。撥水加工のトレーニングウェアとナイキのシューズ。どれもとても頑丈だった。 山手線の駅から駅へ、歩くと自動販売機の灯りの数だけ、路上生活者が小声で歌を歌っていた。賛美歌にも黒人霊歌にも聞こえた。独り言を言ってただけかも知れない。心を一つにしたくても、誰とも繋げる手段を持たない人たちだった。 地下鉄サリン以来、警備がきつくなって今は無理だろうが、当時はシャッターが下りる前に身を潜める場所がいくらでもあった。 ホームレスの暮らしだが、家や事務所を引き払った訳ではないので、家賃滞納額は着実に毎月上がっていた。いくらか現金は、持っていたし、サウナに泊まる事もあったので、ホームレスではなく、路上生活者と呼ぶべきか。 今はどうだか、知らないけど。その時期の東京は、ホームレスというわけでもなく、路上で幾日も過ごす人が多かった。地下街とかは本物のホームレスが主役なので、長くはいたたまれなかった。寒空の下、それこそ路上で過ごす僕たちは、どういう訳か20前後の女と40過ぎの男が多かった。 関東の暴走族伝説というのがあって、その中に僕も登場するらしく。それで皆が血眼で僕を探していた。 どういう訳か、僕は声が出なくなってて、身振りとテレパシーで群集と会話していた。日中の人ごみが奏でる異様な楽音は、オペラのような芝居を僕に強いる。どっちに向かって歩いても僕が波に逆らっている。しょうがなくゴミ箱のすみなどにうずくまる。そうすると、人から僕は見えなくなるのだ。 いよいよ危なくなると、どこか公園を探して寝た。東京の各公園には、それぞれお庭番がいて、どういう訳かそういう時には食事をくれた。しかし元気になると、追い出された。南町田の駅前公園がおまえのお庭だと言われたが、そこに帰りたくはない。だったら家に帰る方がましだからだ。 なぜ家に帰れなくなったのか。帰りたくないという気持ちが先にあるだけで、理由は自分でも分析できなかった。 金とカードは最後まで自分で持っており、何故使えないのか、使いたくないという気持ちがあるだけで、理由は同じく不明だった。 追われているという意識。重要機密が頭の中に埋め込まれているという意識。つかまると殺されるという意識。全て夢だという意識。混乱した頭の上を黒いアゲハチョウが飛ぶ。行き先に迷った時、黒アゲハについて歩く。 知らない人がいきなり話し掛けてくる。民生の人か、スパイか、いずれにせよ歓迎する気にならず、逃げる。大切にしていたテレホンカードに穴があいてたので、何度か何処かに電話したようだ。 「寒いだろ?」そう声をかけてくれる人が多かったから、よっぽど僕は寒い格好をしていたのだろうか。でも全然寒くなかった。特に食べなくても腹はへらなかったし、いつまで歩いても眠くはならなかった。 ただ一箇所にいると見つかってしまうので、誰かにSOSを出しても、迎えに来るまで待っておられず、うろうろしつづけた。 こんな状況の中でも、自分の脳がおかしいのだとは気づかない。変貌したのは社会の方で、見破った自分の英知が正しいのだと思っている。 こんな年でもクリスマスは訪れ。街路樹に飾られた電飾の周りだけ、綿菓子のように雪が光る。たちまち吹きだまる路地に大型テレビの段ボールを敷いて、その上に正座して、イエス様へ十字を切る。雪の粒は僕に触れるとたちまち白い蒸気になってしまう。大理石のデパートの壁を拳で叩いて血まみれにする。アルタの巨大テレビにそんな僕の姿が映っている。 こんなに大勢の人がいて、温もりがあって、手をさし伸ばせば、誰かが握り返してくれる。こんな世界で、何故僕は一人孤独を振り払えないのだろう。 毛細血管のように張り巡らされた光熱水の配管の中で、都会というロボットの中で、生きようとする機能を失った僕という部品は、磨耗した歯車のように空回りばかりしている。東京には僕のような人間がうようよいる。それは昨日の僕で、あれは明日の僕の姿か。 三千台に一台くらい、「日の丸タクシー」というのが東京を走っているのだけど、それだけは、僕の味方なので、見つけたら止めて、花小金井に帰ることに決めていた。そこからまた振り出しに戻るのだけど。 12月末、花小金井で待ち伏せしていた両親につかまり、門司へ連れ戻された。 その時僕には3歳児くらいの抵抗力しか無かった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−14.地下の楽音− 門司に帰り、2度の入院を経た後、2年後、再び東京へ戻って会社員をした。 MRSの有限会社ウエンディは、休眠させたままだった。 平成元年設立時から取締役として働いた会社へ、平社員として再就職した。 株式会社ウエンズという会社。富士通のソフト開発の下請けをしていた。 今は役員より社員の方が待遇がいいとの、社長の有難い判断だった。そのお陰で1年半後に、分裂を再発した時に、傷病手当を1年半、失業保険を3ヶ月、そしてその後に障害年金まで支給される事になろうとは、当時は考えもしなかった事だが。社長はそうなる事がお見通しだったのだろう。 2度入院して、完治した訳ではなかった。状態が落ち着いたのと、東京へ戻りたいという執念が、周りの反対を強引に押し切った。 とりあえず社長の家の一部屋を間借りさせて貰った。有限会社の清算や入院費用などで、貯金は1円も無かった。落ちぶれたもんだ。見る影もない。 枯葉舞う低い初冬の空。 眠れないまま、始発で通勤していた。 目黒から南町田まで。 田園都市線、長津田で急行から各駅に乗り換える時、顔以外正体不明の者が集う。 互いに何する人か知らぬ者達が、ホームに一箇所、一つの灰皿の前に集う。 白い息がタバコでより白くなる。 煙を眺めながら、それぞれの思いをくゆらせる。 会話しない。テレパシーで情報交換する。 比較的新顔の僕だけがうまくコミュニケーション出来ない。皆は同情している。 情けに報いる事が、情報処理か。 停車中の電車から低い5度のハーモニーが響いている。 電車のくせに時折蒸気のようなものを吐く。 エンジンがカチカチ鳴り響く。 通り過ぎる若者のヘッドフォンから漏れるシャカシャカ音。それでも音楽的エクスタシーを誘う。 誰がチューニングした訳でもなく、誰が指揮棒を振るでもなく、やがて恐ろしい交響曲に変わる。 線路脇に咲いた黄色い花が電飾のように点滅している。行き先案内の電光掲示板が世界の終末を告げている。 一応会社員だから、仕事や人間関係など、他の人と共有する世界はある。だが妄想と現実が交差していて、オーム信者の同僚との関係など、どこまでが事実だったのか今も分からない。統一教会やオームとの生きるか死ぬかの戦いが精神世界で繰り広げられ、確実に僕の心は磨り減っていった。一旦落ち着いたかのように見えた病状は、やがてもっと傷を深くしていく事になった。 僕の目や耳から入力された感覚は、脳の中で歪曲されて認識される。僕が認識する時は、すでに変貌した後で、元の世界を窺うことはできない。様変わりしたのは世の中の方で、よもや自分の脳が壊れたなどとは思わない。 精神薬を服用している時には、何にも感動できず、しらーっとした気分で、本を読んでも映画を見ても、ジェットコースターに乗った所で、何も楽しくない。恋も出来ない。だが3、4日飲まないでいると、しだいに感覚が甦り、やがてとがってくる。そして一気に急性期の坂を上る。しょうがない。薬飲んでたんじゃ仕事がこなせないばかりか、会社中を走り回ってしまう。脳がぎりぎりになってから、薬を飲んで休む、落ち着いたら、また薬を抜いて、会社へ出る、そんなパターンが出来ていた。 昼休みを3時間もらって、公園でホームレスと昼寝したり語り合ったりした。 沖縄から出てきた四十代のお庭番に、財布をまかせていた。 東京に住んで十数年。少々の地震には慣れていたけど、この世の終わりかとパニックを起こすようになった。震度3で呼吸が出来なくなった。マグマやプレートのエネルギーが絶対悪の存在を示す。もう東京じゃ暮らせないのか。呪いの交響曲が耳から離れない。 その日、期限が切れる定期券を大切にもっていた。忘れもしない、平成7年7月7日。社長が再び両親を門司から呼び寄せた。繰り返す毎に悪くなる。埼玉の病院に連行され、再び分裂病との診断。門司へ帰って、3度目の入院。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
なっちゃん。現在28歳、既婚、妊娠5ヶ月。小学校2年の時にアル中の父が借金を残して蒸発。母はうつ病で入院。兄妹3人はそれでもたくましく育ち、兄が働き出し、なっちゃんもやっと製糖工場に就職したが、間もなく発病。性格的にはAC。らんま等のアニメが好き。高校時代はワープロ部に在籍。友達はその時の親友が一人だけ。現在夫と作業所で病院の売店やパソコンの仕事をしている。山羊座B型。趣味ビーズ。 厚生労働省殿 精神科病棟の修繕費が他の科より高いとしても、それにはこういう理由があります。早く綺麗にして下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
−16.桃源郷− カラオケのマイクがあった。 「わざわざお集まり頂いて、皆様誠にありがとう」 子供たちが笑っている。 遠い親族が一同に会した、宴がじき始まる。 僕の元服の祝いである。 父母が着替えとか身の回りの物を取りに帰っている間、病棟でそんな事を考えながらたたずんでいた。 初めて入院した33歳の時。もちろん精神病院だという事はわからなかった。 その前にいた世界があまりにも殺伐としていたので、穏やかな療養所。合宿所か何かだと思っていた。僕はここで修行しなければならないのだ。 二十歳前後の若い患者は、皆子供たちに見えた。それ以外は親戚のおいちゃん、おばちゃん。 看護婦さんは皆美しい天使に見えた。 若い看護士さんは、有名サッカー選手たち。 同室の斉藤さんはスーパーマン。渡辺君は宗教家。じいちゃんは、僕の本当の死んだじいちゃん。 そして僕は救世主メシヤの見習い。 ここでは修行の他に改造手術や薬物治療が行われるらしい。 病棟の中心がガラス張りの中空吹き抜けの庭になっていて、竹が長く伸びており、屋上から日が差して天国へ続く階段に見える。 外側の窓には頑丈な鉄格子があり、ここが大切に守られている。外を見ると2階である事がわかる。運動場で誰かが野球をしている。病院の構造物以外に見えるのは、山と空と田畑だけ。 中央に便所があって、その真ん前が食堂。病室は4〜6人部屋が10以上あったと思う。だから当時50人近い人がそこで生活していた。 「米島さん。お注射しましょう」 僕は丁重に断る。 「よっねしっまくん」 と子供たちが誘う。 何故僕の名前を知っていたのか、後で妻に聞くと、シャツの背中に平仮名で大きく「よねしま」とマジック書きしてあったそうだ。 衣類や持ち物に名前を書くよう言われて、多分自分で書いたのだろう。 「なんでもな〜い〜ぃよ。ほら、なんでもな〜い〜ぃわ」 皆が歌っている。後で知ったが五月みどりか誰かの歌謡曲らしい。 「なんでもな〜い〜ぃよ。ほら、なんでもな〜い〜ぃわ」 すぐに覚えて、僕も一緒に歌う。 患者たちは皆家族のようで、昔からの知り合いのようだった。 詰め所(ナースステーション)の前の廊下が、一番賑わった場所で、公衆電話も1台そこに置いてある。 そこでは皆、救済を職員に求めている。 職員は手際よくそれをかわしている。 子供たちが詰め所に入っていくと、しばらくして運動場でサッカーしているのが見える。 本当の出入り口は鉄の扉で常に鍵がかかっている。外へ出るには、詰め所のドアを通って裏から出るしかないのだ。 詰め所のドアが、桃源郷への入り口。 「米島さん。注射しましょう」 再び僕は丁重に断る。 「あなたずっと寝てないんでしょう? 院長から指示が出てます」 しょうがないので、逃げる。 「逃げると保護室へ入れますよ」 声が追いかけてくる。 「入れて下さい」 僕は引き返して丁重にお願いした。 保護室は、詰め所の中にあるので、入りたかったのだ。子供以外は用が無いと入れないような気がしたので。 保護室は窓もなく壁があるだけで、ベッドもなく、布団があるだけで、トイレもなく便器があるだけだった。 鉄格子ごしに明るく暖かい詰め所の中が見える。理事長がタバコをすっている。 アクリルの狭い喫煙室以外の空間でタバコがすえるとは新鮮な光景だ。 誰かが絆創膏を貼ってもらったり、折り紙をしていたり、グラフを書いているのが見える。 うまそうに牛乳を飲んでいる。 「出して下さい」 喉が渇いたし、トイレにも行きたいし、タバコも吸いたくなったので、お願いした。 お願いしても通常は難しいそうだが、僕の場合は、少し待たされたが出してもらえた。 「米島さ〜ん。注射〜」 今度は三人で来た。 何故、さっき打たないの。 ていうか注射されると、今の自分は死んでしまう。 走って、逃げる。 うわっ、今度は走って追いかけてくる。 こっちはしんどくて、足もふらふら。 「殺される〜」 相手は屈強な看護士。しかもサッカーで鍛えてる。 追っかけごっこを子供たちが笑って見ている。 閉ざされた中、ついに腕をつかまれた。 観念するしかない。 打たれてすぐに、気を失う。 3日ほど寝た。 寝てる間に分裂していた人格が統合されてゆく。 体の中の宇宙でぶつかりあう分子が、ちりちりと星のように光った。 目が覚めると、子供たちが僕のベッドを取り囲んでいた。 一人は僕の足元にもたれて寝ていたようだ。 僕と一緒に目を覚まして、 「注射、そんなに怖かった?」 なっちゃんにそう言われて僕は苦笑した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履歴と予定 【履歴】
【予定】 9月中頃にアップする予定でしたが、もう11月。 今、色々書いてますが、スランプ気味。 しばらくは、以下のミュージックライブラリでごまかします。 ミュージックライブラリ お便り待ってます kenchi@wendy21.jp ホームページ けんちん汁 |